1950年代に心理学者アルバート・エリスによって提唱された論理療法(REBT: Rational Emotive Behavior Therapy)は、認知行動療法の基礎を築いた画期的な心理療法です。この療法は、哲学的な思考を取り入れ、人間の考え方そのものに教育的指導を行い、自己実現を支援します。
多くの人が悩みを抱える原因には、「・・・しなければならない!」「・・・するなんて許されない!」といった無意識的に学習した「考え方」が大きな影響を与えていると考えられます。この「考え方=思考」が、苦しみや悲しみなどの否定的な感情を生じさせ、最終的には否定的な行動へとつながるのです。エリスの理論に基づけば、思考や考え方を変えることで、感情や行動も変化し、より幸福で充実した人生を送ることができるとされています。
今回は、論理療法の基本的な考え方やその実践方法、さらには日常生活での応用法について詳しく紹介していきますので、最後までよろしくお願いします。
論理療法の考え方
論理療法は、1950年代にアルバート・エリスによって提唱された心理療法であり、認知療法・認知行動療法のベースとなる認知過程を確立しました。この心理療法は哲学的な思考傾向が強く、人間の考え方そのものに教育的指導を行い、自己実現を支援します。
人が悩みを抱える原因には、「・・・しなければならない!」「・・・するなんて許されない!」など、無意識的に学習した「考え方」が大きな影響を与えていると考えられます。この「考え方=思考」が苦しみや悲しみなどの否定的な感情を生じさせ、最終的には否定的な行動へとつながります。エリスはこの理論を基に、思考・考え方が変われば、感情や行動も変化すると考えました。
アルバート・エリス(Albert Ellis)について
アルバート・エリス(Albert Ellis)は、1913年9月27日にアメリカのペンシルベニア州ピッツバーグで生まれ、2007年7月24日にニューヨークで亡くなった臨床心理学者です。彼は、論理療法(Rational Therapy、後に理性感情行動療法:REBT)を提唱し、認知行動療法の基礎を築いたことで知られています。
エリスは、ニューヨーク市立大学を卒業し、1947年にコロンビア大学で臨床心理学の博士号を取得しました。その後、カレン・ホーナイ研究所で精神分析の訓練を受けましたが、精神分析療法に疑問を感じ、短期で効果的な治療法を模索しました。
1955年に論理療法を提唱し、1959年にはニューヨーク州マンハッタンにアルバート・エリス研究所を設立しました。彼の理論は、出来事(A)と結果(C)の間に信念(B)があり、信念が感情や行動に影響を与えるという「ABC理論」に基づいています。
エリスは、生涯にわたって多くの著書を執筆し、心理学の分野で大きな影響を与えました。彼の主な著書には、「神経症とどう付き合っていくか」(1957年)、「理性的生き方へのガイド」(1961年)、「心理療法における理性と情動」(1962年)などがあります。
エリスの名言として、「人々も出来事も私達をダメにしたりしない。むしろ私達は『自分がダメになってしまう』と信じ込んでしまうことで自分をダメにしてしまう」や、「人生の最良の時期は、自分の問題は自分で背負わなければならないのだと腹をくくった時だ。そのときに自分の運命は自分が支配しているとわかる」などがあります。
人が問題を抱える理論
エリスは、人間が感情的な苦しみ・苦痛を生じる思考過程を「A’B’Cモデル」と名付けました。
- A: 感情が生じるきっかけとなった出来事(体験)
- B: 柔軟で現実対応力が高い思考(ラショナルビリーフ)と、現実的ではなく独断的で論理的ではない思考(イラショナルビリーフ)
- C: 結果として生じる感情や行動
実際のカウンセリング場面では、Bの「イラショナルビリーフ」に着目します。多くの人は、イラショナルビリーフが自然に無意識的に発生するため、認知の歪みに気づきません。そこで、クライエントに気づきを与えるよう指導するのが、論理療法的なアプローチです。
カウンセラーがクライエントに伝えること
論理療法でクライエントに伝えるべきことは、大きく分けて2つあります。
- 否定的な感情の原因は出来事(A)から生じているのではなく、クライエントの認知・思考(B)から生じていること
- 例: 試験で落第点を取った時に「もうダメだ・・・」と深く落ち込む人もいれば、「前より上がった!」と喜ぶ人もいる。同じ「落第点を取った」という事実でも、認知・思考によって生じる感情は大きく異なる。
- 否定的な感情は他人や過去の出来事のせいではないこと
- 人間は、自分の苦しみを過去の養育過程や第三者の責任にしたくなるが、そうすると問題解決に時間がかかるため、「現在の思考・認知」に着目することが重要です。
イラショナルビリーフを伝える
論理療法では、イラショナルビリーフによって苦しむクライエントに対し、その考え方自体に問題があること、もしくはそのような考え方が間違っていることに気づかせます。
カウンセリング場面でよく見られるイラショナルビリーフの例:
- マイナス思考: 良いことを無視し、何でも悪い出来事にすり替える。
- 拡大解釈・過小評価: 自分の短所や失敗を大げさに考え、長所や成功を過小評価する。
- 感情的決めつけ: 客観的事実より否定的感情を堅実だと決めつける。
- すべき思考: 何かをやる時に「・・・すべき」「・・・すべきでない」と考える。
- 一般化し過ぎ: 一つ悪いことがあると、「いつもこうだ」「上手くいったためしがない」と考える。
- 極端なレッテル貼り: 失敗した時に自分に対して極端にネガティブなレッテルを貼る。
- 結論の飛躍: 特に確かな理由もないのに深読みや先読みをして悲観的・否定的な結論を出す。
論理療法の基本的な流れ
論理療法カウンセリングは、来談者中心療法のようにクライエントの自由な語りに任せるのではなく、あらかじめ構造化された枠組みの中で進められます。初めはカウンセラーがリードし、以下の過程で進めます。
- 前回のカウンセリングで残った課題
- 気分・症状のチェック
- 生活上の大きな変化の報告
- ホームワークの確認
- 今日話すことの設定
- 今日のカウンセリングのまとめ
- 次回までのホームワーク
- 質問
時間配分の目安としては、1〜4で10分、5〜6で30分、7〜8で10分、計50分を想定します。
カウンセラーの具体的な関わり
論理療法を用いる場合、カウンセラーはまずクライエントにカウンセリングの構造(流れ)を示す必要があります。
初めの2〜3回のカウンセリングで目標(ゴール)を定め、カウンセラーとクライエントが協力してカウンセリングを進めます。具体的な問題解決(B イラショナルビリーフに着目する)の前に、クライエントのC(感情的問題)に着目することが論理療法の特色です。クライエントに共感を示し、「どのような感情状態になれば気持ちが楽になるのか」を聴き取り、あらかじめ感情的問題を取り上げます。
そうすることで、否定的な感情が問題解決の妨げにならず、スムーズに学習を進める環境を整えます。
まとめ
論理療法(REBT)は、アルバート・エリスによって提唱された心理療法であり、認知行動療法の基礎を築いた画期的なアプローチです。私たちの日常生活においても、エリスの理論を取り入れることで、より健全で前向きな思考を持つことができます。
思考や考え方が変われば、感情や行動も変化し、結果としてより幸福で充実した人生を送ることができるでしょう。本ブログを通じて、論理療法の基本的な考え方やその実践方法、そして日常生活への応用法について理解を深めていただけたでしょうか。今回も最後まで読んでいただきありがとうございました。次回もよろしくお願いします。
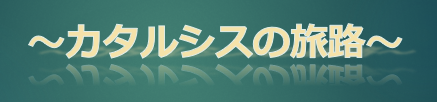
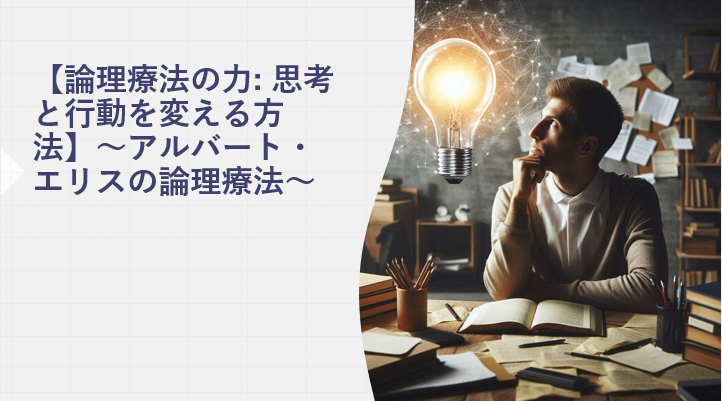

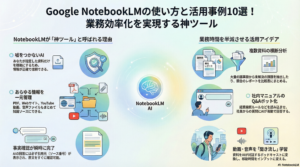
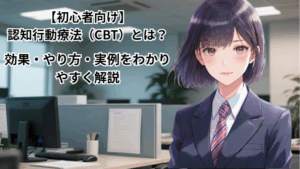
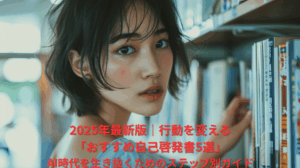

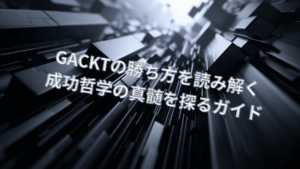


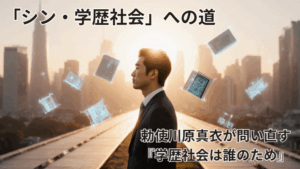
コメント