皆さん、こんにちは! 今回は、3年くらい前にたまたまネットで見つけた記事で印象に残っている言葉で、「どんなに仕事ができても。最後はやっぱり人間力だからな。悪口や陰口は言うな。挨拶と時間はきちんとしろ。自分の機嫌は自分で取りなさい。また会いたいと思われる人間を目指しなさい」という言葉があります。そんな「また会いたい」と思われるような人間になるための方法を学ぶことができる本をビジネス書から小説まで多岐にわたるジャンルで1000冊以上の著書を持つ中谷彰宏さん著書の”「また会いたい」と思われる人「二度目はない」と思われる人”について紹介をしていきたいと思いますので最後までよろしくお願いいたします。
皆さんは、仕事やプライベートで一度会った人に二度目は会ってもらえなかったという経験はありますか?
私自身、結構経験があります。
この本は「二度目はないな」と思われてしまいがちな人と「また会いたいな」と思われる人との違いについて具体的な事例を踏まえて解説がされておりとてもわかりやすいです。この本を読めば「また会いたい」と思われる人の思考や言動を学べるのでいくつか紹介していきます。
一度目の出会いを大切にする
基本的に、人と人との出会いは、一度目があって、その後二度と会わないか、あるいは三度目、四度目と続く関係になるかのどちらかです。つまり、相手と関係を築きたいのであれば、「また会いたい」と思われる人になる必要があります。一度会ってもらったからといって、二度目、三度目があるだろうと考え、最初の出会いを大切にしないと、その後の関係は続きません。「また機会があれば…」や「何かあれば…」では、その「機会」や「何か」はいつまで経ってもやって来ないのです。
特にビジネスの場では、その人に会う前から「こういうことをしましょう」と具体的な内容でアプローチすることが重要です。要するに、最初の出会いは、誰かの紹介や運による部分が大きいので、二度目や三度目があるとは思わずに、最初の出会いを大切にし、全力で取り組むことが大切です。

相手の質問には具体的に回答をする
短い受け答えであっても、「また会いたい」と思われるか、「次はないな」と思われるかが決まることがあります。例えば、「ご出身はどちらですか?」と質問された際、ある人は「関西です」と答え、別の人は「神戸です」と答えたとします。「関西です」と答えた場合、その後の会話は広がりにくいでしょう。一方で、「神戸です」と答えると、「神戸といえば最近ポートタワーがリニューアルされましたよね」や「神戸といえば中華街が有名ですよね」といった会話が生まれやすくなります。
相手の質問に対して曖昧な答えをするのは、「個人情報を知られたくない」という心理的なブロックが働いており、相手には「それ以上踏み込まないでほしい」というネガティブな印象を与えることがあります。
例えば「あなたの趣味は?」と聞かれた際に「食べ歩きです」と答えるよりも、「食べ歩きが好きで、最近だと南京町で食べ歩きをして老祥記の豚まんが美味しかったです」と具体的に答えるほうが、相手の印象に残りやすく、さらに「老祥記って有名で、かなり並んだんじゃないですか?」と会話を広げることができます。

おもてなしは準備の苦労を表にださないこと
おもてなしは目に見える部分ではなく、目に見えない部分で勝負しなければなりません。華やかなおもてなしの裏側こそが、本当のおもてなしと言えるのです。
例えば、うなぎ職人には「串打ち三年、裂き八年、火鉢一生」という言葉があります。美味しいうなぎを焼くには、膨大な時間と努力が必要です。良いうなぎを仕入れることも容易ではありません。一流のうなぎ屋の大将は、「自分は何年も修行を積んだ」や「このうなぎを仕入れるのに10年かかった」といったことを口にすることはありません。
こうした苦労や準備を表に出さないことが、本当のおもてなしだと言えるのです。見えない準備にこそ勝負があり、その結果として、次に繋がる関係性が生まれるのです。

受け身になって話しかけるのを待たない
「いい出会いがない」「話す人がいない」と感じている人の特徴の一つに、「いつも話しかけられるのを待っている」という点があります。飲み会や懇親会、パーティーなどの社交の場で、自分の席でじっと座って誰かに話しかけてもらうのを待っているだけでは、せっかくの出会いのチャンスを無駄にしてしまいます。スマホを触っているのは論外です。成功している一流の人ほど、自分から積極的に話しかけています。
例えば、松下幸之助さん(Panasonicの創業者)は、新幹線で京都駅から東京駅に向かう途中、別々の車両に乗っていた20歳ほど年下の知人に、名古屋駅で降りる際、わざわざホームに降りてまで挨拶をしたそうです。こうした行動が、彼を多くの人に「また会いたい」と思わせ、その結果として成功を手にしたのです。
「誰も話しかけてくれない」といじけてスマホを見ているのではなく、まずは自分から積極的に話しかけることが大切です。

ライバルを紹介する
顧客本位の姿勢は、長期的な信頼関係を築くために不可欠です。自分の店で対応できない場合や顧客のニーズに合わない場合でも、ライバル店を紹介できることは、顧客を本当に思いやっていることを伝える一つの方法です。これにより、顧客は「この人は自分のことを考えてくれている」と感じ、信頼を得ることができます。
短期的な利益を追い求めず、顧客にとって最適な選択肢を提示する姿勢は、信頼と誠実さを生み出します。たとえ他の店を紹介しても、自分の利益にはつながらないように見えても、顧客からは「この人に相談すれば間違いない」と思われるようになり、結果としてリピーターや紹介客が増えることがあります。
例えば、飲食店で「今日はうちの店は満席ですが、近くの○○さんの店なら美味しくて空いているかもしれませんよ」と教えてくれる店員がいれば、その店員に対する信頼感は大きくなります。このように、短期的な売上を重視するのではなく、顧客との信頼関係を大切にすることが、結果的には自分の評価を高め、ビジネスにとっても有益であることを示しています。

気配りは相手の優先順位を想像すること
相手の優先順位を想像し、そのニーズに合わせて配慮することは、良い人間関係を築くために非常に重要です。
相手の優先順位を想像する
たとえば、ビジネスの会話で相手が時間に厳しく、効率を重視している場合を考えてみましょう。もしあなたが無駄話をしてしまったら、その相手は不快に思うかもしれません。しかし、要点を簡潔に伝えれば、その人は「時間を無駄にされなかった」と感じ、信頼を得られます。逆に、相手が人間関係を大切にしている場合、少し時間をかけて心のこもった言葉を使うと良い印象を与えることができます。
相手にとっての重要な事柄を重視する
例えば、初めて会った人が健康や家族を大切にしているとします。その時、あなたがその人に「最近はどうですか?」と話しかける際に、健康や家族について関心を示すと、その人は「自分の大事にしていることを理解してくれている」と感じ、信頼感が増します。逆に、これらを無視して、仕事の話ばかりしてしまうと、その人はあなたに対して距離を感じるかもしれません。
自分中心ではなく相手中心で考える
例えば、ある人が何か困っているときに、自分がその問題についてどう感じているかを話すのではなく、相手が何を求めているのかを理解してサポートすることが大切です。自分の意見を押し付けるのではなく、相手が聞きたいことや求めていることに耳を傾け、最適な方法で接することで「また会いたい」と思ってもらえるでしょう。
柔軟な対応
例えば、ある人には堅実で礼儀正しく接し、別の人にはフレンドリーに接することが大切です。人によって、求めている接し方や対応が異なるため、その場その場で相手の気持ちに合った対応をすることが重要です。例えば、ビジネスマンにはプロフェッショナルな態度を、友達にはリラックスした雰囲気で接することで、どちらの人にも良い印象を与えることができます。
このように、相手の優先順位を理解し、その人に最適な配慮をすることで、信頼を得られ、「また会いたい」と思われる存在になれるのです。正直、面倒くさいことかもしれませんが、面倒くさいことをあえてやることが大切です。

大切な人と会うときはスマホの電源を切る
中谷彰宏さんの「大切な人と会うときはスマホの電源を切る」という言葉は、相手との時間を大切にし、真摯に向き合うことの重要性を強調しています。スマホがあると、無意識に通知を確認したりすることがあり、相手に対して十分に集中できません。スマホの電源を切ることで、相手に「今、この瞬間はあなたに集中している」と伝えることができます。
例えば、ある友人とカフェで会う約束をしたとき、友人が話している最中にあなたがスマホをいじっていると、友人は「自分の話に興味がないのでは?」と感じるかもしれません。しかし、スマホを切ってその時間を大切にすると、友人は「この人は私に対して心から関心を持っている」と感じ、会話がより深く、豊かなものになります。
スマホを使わないことで、相手は自分が大切にされていると感じ、信頼関係が深まります。また、スマホを切っていると、相手は安心し、会話がより自然で深くなり、質の高いコミュニケーションが生まれます。簡単な行動ですが、スマホを切ることで、相手に対する思いやりを示し、絆を強めることができます。

出会いの貴重さに気づく
出会いの際には、相手に対して真摯で誠実な態度を示すことが大切です。相手がどんな人物で、何を大切にしているかを理解し、それに基づいて接することで良い印象を与えることができます。初対面では、その瞬間が貴重であることを意識し、相手に心地よさを与えるよう心がけることが重要です。例えば、相手の話にしっかり耳を傾け、コミュニケーションを取ることで「また会いたい」と思わせることができます。しかし、初対面の印象だけではなく、その後も相手に対して丁寧に対応し、信頼関係を築くことが大切です。最初の印象を良くするだけでなく、その後の行動や態度が相手との関係を深める鍵となります。
例えば、仕事で初めて会ったクライアントに対して、最初の会話できちんと挨拶をし、相手の話にしっかりと耳を傾け、丁寧な対応をすることで、「この人とまた会いたい」と感じてもらうことができます。しかし、初対面で無礼だったり、相手の話を聞かずに自分だけの話を続けたりすると、その後、二度目の会話はないかもしれません。

まとめ
『「また会いたい」と思われる人「二度目はない」と思われる人』を通して、改めて感じたのは、人間関係の基本は「思いやり」と「誠実さ」であるということです。ビジネスにおいても、プライベートにおいても、相手を大切にし、その時々に最適な対応を心掛けることで、信頼関係が築かれ、何度でも会いたいと思わせることができるのです。どんなに仕事ができても、人としての魅力や人間力があってこそ、その後の関係が続いていくことを改めて実感しました。
また、何気ない日常の中でも、相手に対して誠実に接し、思いやりのある行動をすることが、結果的に自分の評価を高め、良い人間関係を築くための鍵となります。「また会いたい」と思われる人になるために、普段からの小さな心掛けや行動が大切だと感じます。この本で紹介されている方法は、すぐに実践できるものばかりなので、ぜひ日常生活に取り入れて、より良い人間関係を築いていきたいものです。
皆さんも、これからの出会いを大切にし、「また会いたい」と思わせるような人間になれるよう、努力していきましょう。それがきっと、ビジネスやプライベートのどちらにおいても、幸せを引き寄せることにつながるはずです。
最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。皆様も中谷彰宏氏の著書人間関係を築くために大切なこと—中谷彰宏の「また会いたい」と思われる人の法則をぜひ一度お手に取ってご覧いただければ幸いです。また次回の投稿もどうぞお楽しみに。皆様のご意見やご感想をお待ちしております。今後ともよろしくお願い申し上げます。
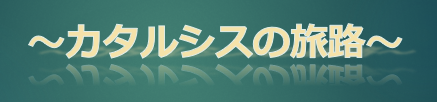
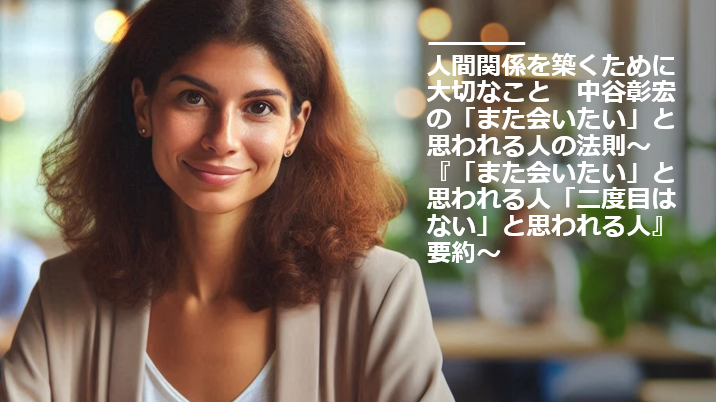

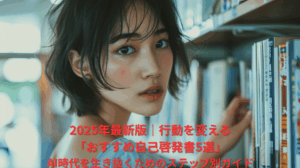

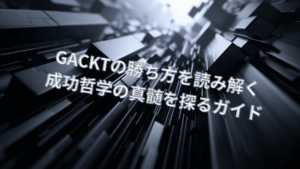


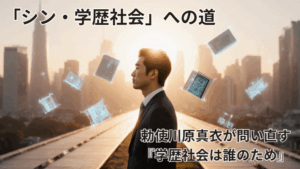


コメント