こんにちは。 突然ですが、あなたは最後に本を一冊読み切ったのがいつか、覚えていますか? 「最後に読んだのは学生時代かな……」という方も、きっと少なくないはずです。 毎日が忙しくて、スマホを見る時間はあっても、じっくり本を開く時間はなかなか作れないものですよね。 けれど、そんな「読書から少し離れているあなた」にこそ、どうしても手に取ってほしい一冊があるんです。 それが、今回ご紹介する住野よるさんのデビュー作、『君の膵臓(すいぞう)を食べたい』です。 このタイトルを見て、あなたはどう感じましたか? おそらく、多くの人が「えっ、ホラーなの?」と驚いたり、「ちょっと怖そう」と距離を置いたりしたくなるでしょう。 実は、私もそうでした。 でも、安心してください。 これは決して怖いお話ではありません。 それどころか、読み終えた瞬間に、この言葉がこの世で一番美しい「愛の告白」に見えてくる、とても不思議で温かい物語なんです。 私は、物語には人の心を癒やしたり、明日を生きる活力を与えたりする特別な力があると信じています。 一冊の本との出会いが、あなたの人生の景色をガラリと変えてしまうことだってあるのです。 今回は、読書が苦手な方でも物語の情景がふんわりと浮かぶように、できるだけ分かりやすい言葉でお話ししていきますね。 肩の力を抜いて、物語の扉をそっと叩いてみてください。 ここからは、この物語がなぜこれほどまでに多くの人の心を掴んで離さないのか、その理由を一緒に探っていきましょう。
第1章:ファーストコンタクト
SNSや口コミで話題になった「謎の言葉」
SNSのタイムラインや、本屋さんのポスターで、この不思議な言葉を一度は見かけたことがあるのではないでしょうか。 「君の膵臓を食べたい」。 初めてこの文字を目にしたとき、ほとんどの人が「えっ、どういうこと?」と足を止めたはずです。 それくらい、この言葉が持つインパクトは強烈でした。 ネットやSNSでも、「タイトルは怖いけど、実はめちゃくちゃ泣けるらしい」という口コミが瞬く間に広がっていきました。 多くの人が、最初は半信半疑だったのです。 「本当にこのタイトルで感動なんてするの?」と、少し疑ってしまうのも無理はありません。 でも、その「謎」こそが、この本がベストセラーになった大きなきっかけでもありました。 みんな、このタイトルに隠された本当の意味を知りたくて、たまらなくなったのです。 話題になればなるほど、この言葉は単なる「不気味なフレーズ」から、何か特別な意味を持つ「秘密の合図」のような存在になっていきました。 もしあなたが、この言葉をどこかで聞いて「自分には関係ないかな」とスルーしていたとしたら、それはとてももったいないことです。 なぜなら、多くの人がわざわざ誰かに教えたくなるほどの「驚き」が、この言葉の先には待っているからです。
グロテスク?いいえ、究極の純愛です
確かに、「臓器を食べる」という表現だけを聞くと、少し不気味に感じるかもしれません。 でも、この物語の中で語られるその言葉には、ドロドロした怖さは一切ありません。 むしろ、透き通るような純粋さと、相手を想う切ない気持ちがぎゅっと詰まっています。 昔の言い伝えでは、自分の体の悪い部分と同じ動物の部位を食べると、病気が治ると信じられていたそうです。 ヒロインの桜良は、病気で弱っている自分の膵臓を治したいという願いを込めて、最初は冗談めかしてこの言葉を使います。 でも、お話を読み進めていくうちに、この言葉のニュアンスが少しずつ変わっていくことに気づくはずです。 それは「あなたの病気を治したい」という願いから、「あなたの一部になりたい」「あなたを私の中に残したい」という、もっと深い祈りへと変化していきます。 相手の魂を丸ごと受け入れたいと願うとき、人はこんなにも真っ直ぐな言葉を選ぶのかもしれません。 恋人や友達といった既存の言葉では、到底足りないくらいの強い絆。 その特別すぎる関係を表現するために、このタイトルはどうしても必要だったのです。

読み終えた瞬間に「180度変わる」タイトルの意味
本を読み始める前と、最後の一行を読み終えたあと。 あなたの手元にあるその本のタイトルは、まったく別物に見えているはずです。 最初はあんなに違和感があった言葉が、最後には涙なしでは読めない、かけがえのないメッセージに変わっています。 これが、作者の住野よるさんが仕掛けた、最高の「魔法」なんです。 物語のラストにたどり着いたとき、あなたはきっと、自分のこれまでの価値観が180度ひっくり返るような衝撃を受けるでしょう。 「食べたい」という言葉が、こんなにも優しく、切なく、そして力強いものだったなんて。 多くの読者が「このタイトルの意味を知るために、もう一度最初から読み直したい」と口を揃えます。 それは、言葉の裏側にある二人の「生きた証」を、全身で受け止めた証拠でもあります。 タイトルに込められた本当の重みを知ったとき、あなたの心には、温かい何かがじんわりと広がっていくはずです。 そして、この本を閉じたあと、あなたはもう二度と、このタイトルを「怖い」なんて思うことはないでしょう。

第2章:「正反対」だからこそ惹かれ合う、二人の個性
名前を持たない「僕」:他人と関わりたくない少年
さて、ここからは物語を彩る魅力的な二人について、もう少し詳しくお話ししていきますね。 まずは、物語の語り手である主人公の「僕」です。 彼は、クラスの中でも存在感がなく、いつも一人で本を読んでいるようなタイプです。 他人に興味を持たず、自分だけの世界に閉じこもることで、自分を守って生きている少年。 実は物語の後半まで、彼の「名前」は伏せられたまま進んでいきます。 それは、彼が「自分は誰にとっても特別な存在ではない」と思い込んでいることを表しているかのようです。 あなたは、自分のことを「平凡で、誰の記憶にも残らない人間だ」なんて思ったことはありませんか? 「僕」の姿を見ていると、どこか自分の一部を見ているような、不思議な親近感を覚えるかもしれません。 そんな彼が、ある一人の少女との出会いによって、少しずつ、でも確実に外の世界へと踏み出していくことになります。
ひまわりのような「桜良」:秘密を抱えた人気者
彼女は、クラスの誰もが憧れるような、太陽のように明るい女の子です。 いつも笑顔で、周りには自然と友達が集まってくるような、絵に描いたような人気者。 でも、そんな彼女の体の中には、誰にも言えない重い秘密が隠されていました。 膵臓の病気によって、彼女に残された時間はあとわずかだったのです。 普通なら絶望してしまいそうな状況なのに、彼女は自分の運命を恨むことも、悲劇のヒロインを演じることもしません。 むしろ「死ぬまで、私は精一杯生きるよ」と決めているかのように、一日一日を大切に笑って過ごします。 その強さと健気な姿に、読んでいる私たちはいつの間にか心を奪われ、彼女の幸せを願わずにはいられなくなります。
「正反対のパズル」がカチッとハマる瞬間
まったく違う世界に住んでいた二人が、偶然のきっかけで出会います。 一人は「他人を必要としない」ことで自分を守り、もう一人は「他人に囲まれる」ことで自分を保っていました。 まるでバラバラなパズルのピースのように見えますが、実はお互いに足りないものを補い合える存在だったのです。 正反対だからこそ、今まで知らなかった新しい景色を見せ合えるようになります。 彼が彼女に与えたのは、秘密を共有する相手という「安心感」でした。 そして、彼女が彼に与えたのは、誰かと関わることの「温かさ」だったのです。

第3章:運命の出会い
病院の待合室という、日常の中の非日常
すべての始まりは、どこにでもある病院の待合室でした。 主人公の「僕」は、虫垂炎の抜糸のためにたまたまそこを訪れていました。 診察を待つ間の、なんてことのない退屈な時間。 そこで彼は、ソファの上に一冊の文庫本が置き忘れられているのを見つけます。 その本の表紙には、手書きで『共病文庫』という不思議なタイトルが書かれていました。 中をパラパラと開いてみると、そこには衝撃的な事実が綴られていたのです。 「私の膵臓は、もうすぐ動かなくなります」。 この何気ない拾い物が、関わるはずのなかった二人の運命を、一本の線で結んでしまうことになりました。
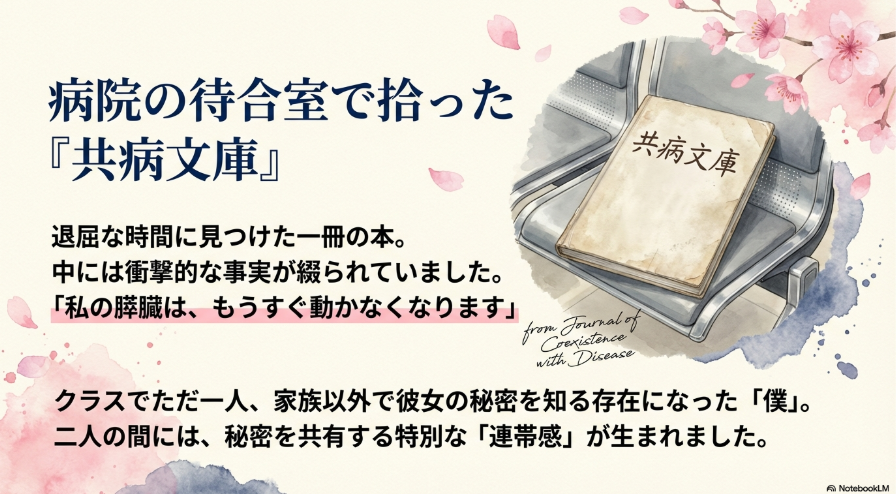
秘密を共有することの「特別感」
秘密を共有するというのは、その瞬間に世界に「二人だけの居場所」ができるようなものです。 他のクラスメイトは誰も知らない彼女の病気。 それを知っているのは、家族を除けば、世界中で「僕」だけでした。 この「特別なつながり」が、二人の間に不思議な連帯感を生み出していきます。 本当は誰とも関わりたくなかった「僕」ですが、彼女の強引なペースに巻き込まれ、秘密を守り続けることになります。 そして、その役割を全うしようとする中で、いつの間にか彼女にとって不可欠な存在になっていくのです。
クラスメイトという枠を超えた、奇妙な関係の始まり
二人の関係は、名前を付けるのがとても難しいものです。 ただの「クラスメイト」にしては、あまりにも重く深い秘密を共有しすぎています。 かといって、すぐに甘酸っぱい「恋人」と呼ぶには、どこか淡々としていて、お互いに一線を引いているような空気も漂っています。 この既存の枠組みにはまらない「名前のない関係」こそが、読んでいる私たちの心をざわつかせ、好奇心をくすぐります。 物語は、この不思議な絆を大切に育みながら、静かに、でも着実に進んでいくのです。
第4章:日常の煌めき
スイーツバイキングで見せた、普通の女の子の顔
彼女が「僕」を強引に連れ出したのは、街にある賑やかなスイーツバイキングでした。 死を目前に控えた女の子とは思えないほど、彼女は目をキラキラさせてお皿いっぱいにケーキを並べます。 その無邪気な笑顔を見ていると、「彼女がもうすぐいなくなる」という残酷な現実を、ついつい忘れてしまいそうになります。 彼女にとって、こうした「普通」の時間が、どれほど愛おしく、価値のあるものだったのでしょうか。 特別なイベントではなく、何気ない食事やお喋りの中にこそ、本当の幸福が隠されていることを、彼女の姿は静かに教えてくれます。
一泊二日の旅行:二人の距離が急接近した夜
次に彼女が提案したのは、新幹線に乗って遠くへ出かける一泊二日の旅行でした。 学校や親には内緒で、秘密を共有する二人だけの特別な逃避行です。 目的地へ向かう車中での何気ない会話や、現地の美味しいものを食べる時間。 そんな時間が積み重なるたびに、彼の中にある「他人を拒絶する壁」が、少しずつ低くなっていくのがわかります。 しかし、楽しい時間の中でも、ふとした瞬間に「彼女の病気」という現実が顔をのぞかせます。 ホテルの部屋で、彼女の鞄に大量の薬や注射が入っているのを見て、彼は改めて突きつけられるのです。 目の前で笑っているこの少女が、本当に消えてしまうかもしれないという事実に。
「真実か挑戦か」ゲームで明かされる本音
その夜、ホテルの部屋で二人は「真実か挑戦か」というゲームを始めます。 トランプで勝った方が、相手に質問をするか、あるいは何かを実行させるか選べるという遊びです。 一見するとただの暇つぶしのように思えますが、このゲームを通して二人は、普段は口にできない「心の奥底」をさらけ出していくことになります。 「私が本当に死ぬのが怖いと思っているか、聞きたい?」 冗談めかした彼女の問いかけに、彼は答えに詰まってしまいます。 質問を重ねるたびに、二人の距離は肉体的な近さ以上に、魂の部分でぐっと近づいていきました。 相手の本当の姿を知りたいという切実な願いが、この夜の空気を特別なものに変えていたのです。

第5章:桜良の哲学
「死ぬまで、私は生きるよ」という力強い宣言
彼女は自分の運命を嘆く代わりに、ある力強い言葉を口にします。 「死ぬまで、私は生きるよ」。 当たり前のことのように聞こえますが、余命宣告を受けた彼女が言うからこそ、この言葉には震えるほどの重みがあります。 彼女にとっての「生きる」とは、ただ心臓が動いていることではありません。 誰かと心を通わせ、誰かを認め、自分の意志で何かを選択すること。 それが彼女にとっての「生きる」という定義だったのです。 彼女のこの真っ直ぐな生き方は、自分を閉ざしていた彼の価値観を、根底から揺さぶり始めます。
運命ではなく、自分の「選択」でここにいる
私たちはよく、素敵な出会いがあると「これは運命だね」なんて言ったりします。 でも、桜良はそれをはっきりと否定します。 「私たちがここで出会ったのは、運命なんかじゃないよ」と。 彼女は、自分がこれまでに積み重ねてきた無数の「選択」が、自分を今の場所に連れてきたのだと考えていました。 彼が病院で本を拾うという選択をし、彼女がその秘密を彼に打ち明けるという選択をした。 そうした一つひとつの決断が重なり合って、今の二人の時間が生まれているのです。 「運命」という言葉で片付けてしまうのは、自分の人生を人任せにしているのと同じことかもしれません。 自分の意志で選んで、誰かと一緒にいることの尊さを、彼女の言葉は鋭く教えてくれます。
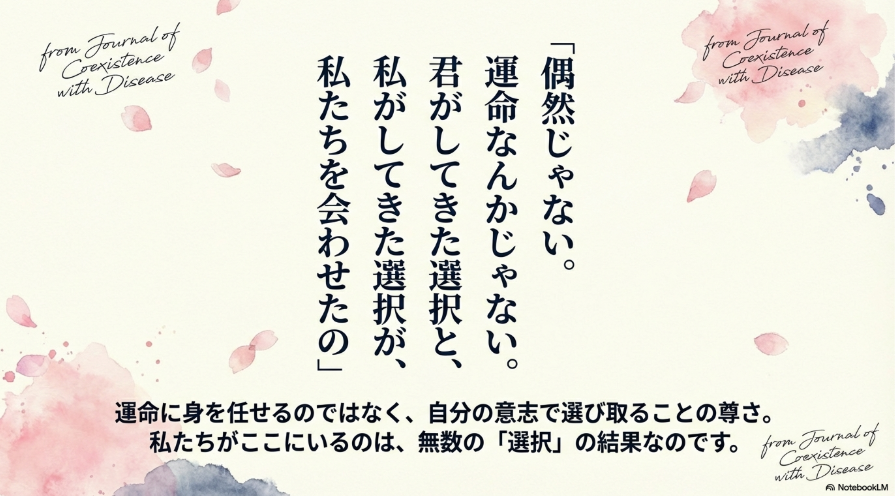
「誰かと心を通わせること」が生きる意味
桜良にとって、「生きる」とは一体どういうことだったのでしょうか。 彼女は言います。 「誰かと心を通わせること。誰かを認めること。誰かを好きになること」。 もし世界に自分一人しかいなければ、自分が生きているのかどうかさえ、きっと分からないはずです。 誰かと関わり、感情を動かし、お互いの存在を認め合うこと。 その「つながり」の中にこそ、人が生きる本当の理由があるのだと彼女は信じていました。 たとえ残された時間が短くても、その一瞬一瞬で誰かの心に触れることができれば、それは十分に「生きた」ことになる。 孤独を愛していた「僕」にとって、この考え方は雷に打たれたような衝撃だったに違いありません。
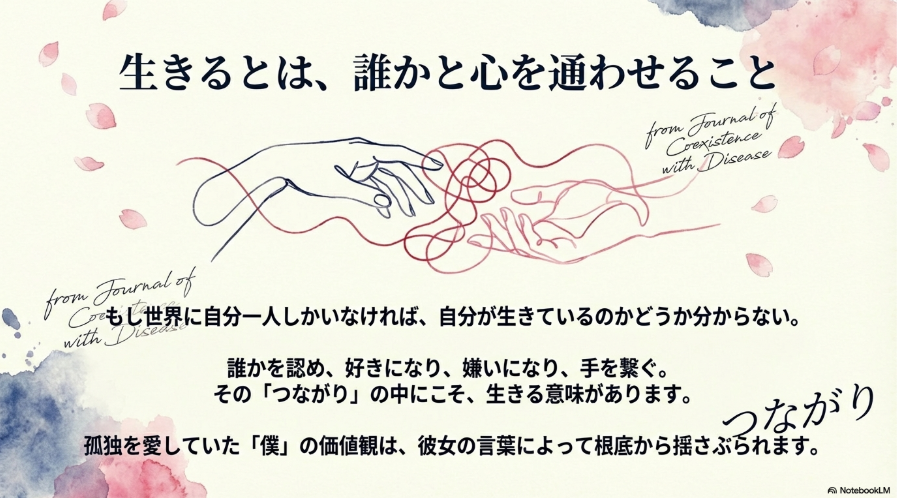
第6章:「恋」でも「友情」でもない、別の何か
既存の言葉では縛れない、二人の絆
物語を読み進めていくと、私たちはある「もどかしさ」を感じるようになります。 「この二人は付き合っているの?」「それともただの親友なの?」という疑問です。 しかし、そのどちらの言葉もしっくりときません。 彼らの関係は、もっと純粋で、もっと切実で、もっと深い場所にあります。 恋人という形に当てはめてしまうには、あまりにも魂の結びつきが強すぎるのです。 彼らはお互いを、単なる「好きな人」として見ているのではありません。 自分にないものを持つ相手を敬い、その存在を丸ごと自分の中に刻み込もうとしています。 この「名前のない関係」にこそ、私たちが言葉にできない大切な感情が隠されています。
憧れと、嫉妬と、深い慈しみ
二人がお互いに抱いていたのは、単純な「好き」という言葉だけでは説明できない複雑な感情でした。 彼は、自分にはない彼女の明るさや、誰からも愛される力に強く憧れていました。 それは同時に、自分には決して手が届かない眩しさに対する、ほんの少しの「嫉妬」でもあったのかもしれません。 一方で、自由奔放に見える彼女もまた、誰にも頼らずに一人で凛としていられる彼の強さに、深い尊敬と憧れを抱いていました。 お互いが「自分にないもの」を相手の中に見つけ、それを心から尊いと感じていたのです。 自分に足りないピースを相手が持っているからこそ、相手を慈しむ気持ちは、自分自身を大切にするのと同じくらい深くなっていったのでしょう。
「君になりたかった」という究極の共感
「君になりたい」。 物語の中で、二人がお互いに対して抱くこの思いは、このお話の核心に触れるとても大切なポイントです。 相手を大切に想うということは、単に「一緒にいたい」と願うだけではありません。 その人の生き方そのものを尊敬し、自分の中に取り入れたいと心から願うことでもあります。 彼が彼女のようになりたいと願い、彼女が彼のようになりたいと願う。 この究極の共感こそが、二人をただのクラスメイト以上の、魂のパートナーへと変えていったのです。 相手を自分の中に受け入れようとするその姿勢が、最後にあの一行へと繋がっていくことになります。

第7章:衝撃の展開
私たちが忘れている「死は平等にやってくる」という事実
私たちは普段、明日が来ることを当たり前のように信じて疑いません。 でも、この物語はそんな私たちの甘い考えを、音を立てて打ち砕きます。 「死は、病気の人にだけ順番にやってくるわけではない」という残酷な現実を、突きつけてくるのです。 桜良は病気でしたが、それでも彼女の最期は、私たちが想像していたものとはまったく違う形で訪れます。 それは、どれほど準備をしていても、どれほど覚悟を決めていても、命は一瞬で消えてしまうことがあるという教訓のようでもあります。 このあまりにも突然の出来事に、「僕」も、そして読んでいる私たちも、言葉を失い、深い衝撃を受けることになります。
あまりにも突然の、そして残酷な別れ
私たちはどこかで、彼女の最期は病院のベッドの上だろうと思い込んでいました。 静かに息を引き取って、彼がその手を握るような、そんな悲しいけれど美しい別れを想像していたのです。 でも、現実はもっとずっと、無慈悲で予測不能なものでした。 待ち合わせの場所に彼女は現れず、代わりに彼が目にしたのは、テレビから流れるニュースの速報でした。 病気ではなく、まったく関係のない事件によって、彼女の命はあまりにもあっけなく奪われてしまったのです。 「明日会おうね」という約束が、二度と果たされることのない永遠の別れになってしまった瞬間。 そのあまりの理不尽さに、胸が締め付けられ、ページをめくる手が止まってしまうかもしれません。 命の灯火が消えるとき、そこには理由も順番も存在しないのだという事実が、私たちの心に重くのしかかります。
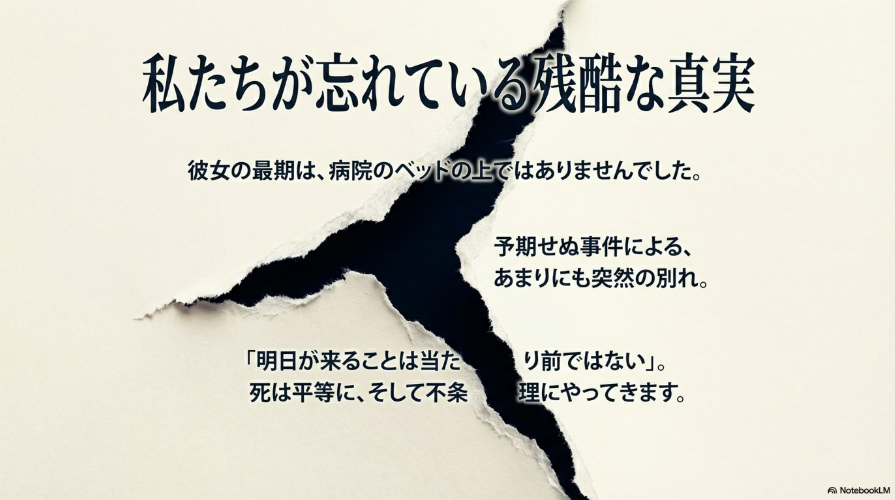
残された者が受け取る、最後の手紙
彼女がいなくなったあとの世界は、まるで色が抜けてしまったかのように静まり返っています。 彼は深い喪失感の中で、彼女が残した『共病文庫』を手に取ります。 そこには、彼がずっと聞きたかったこと、そして彼女が最後に伝えたかったことのすべてが記されていました。 日記のページをめくるたび、彼女がどれほど彼を必要としていたか、どれほど彼に救われていたのかが溢れ出してきます。 一文字一文字が、彼女の温もりを運んできて、止まっていた彼の時間を再び動かし始めます。 形としての彼女はいなくなっても、彼女の言葉は、これからを生きていく彼にとっての「光」となって残されたのです。
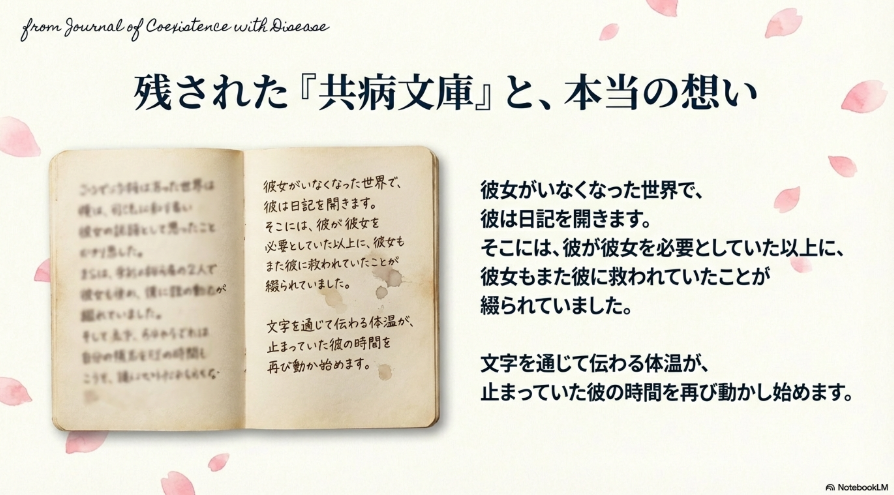
第8章:タイトルの回収
太古の信仰と、現代の愛が交差する言葉
物語のクライマックスで、ついにあの衝撃的なタイトルがふたたび姿を現します。 かつての人々が「大切な人の魂を自分の中に取り込みたい」と願ったとされる、古い言い伝え。 それは、病気を治したいという願いを超えて、相手の生き方そのものを自分の中に刻みたいという、究極の意志表示でした。 「君の膵臓を食べたい」。 この言葉は、単なる好きという感情を超えた、祈りにも似た愛の形だったのです。
魂を自分の中に取り入れたいという熱望
人は、誰かを心から大切に想ったとき、その人のすべてを独り占めしたいと願うことがあります。 でも、彼女が望んだのは、もっと深いレベルでの「結びつき」でした。 「食べる」という行為は、相手を自分の一部にし、一生離さないということです。 彼女の強さも、太陽のような明るさも、そして彼女という存在そのものを、自分の中に永遠に留めておきたい。 そんな切実な願いが、この言葉には込められています。 彼もまた、彼女がいなくなったあとの世界で、彼女の意志を引き継いで生きていこうと心に誓います。 相手の魂が自分の中で生き続け、共に歩んでいくこと。 それこそが、死さえも乗り越えることができる、唯一の方法だったのかもしれません。
読者が一生忘れられなくなる「最高の告白」
物語の最後に放たれるこの言葉は、どんな「好き」や「愛してる」よりも重く、深く心に響きます。 なぜなら、この言葉には二人が共に過ごした時間のすべてがぎゅっと詰まっているからです。 スイーツバイキングでの笑い声や、旅先での夜の静寂、そして二人だけで守り通した秘密。 それらすべてをひっくるめて、「君という人間になりたい」と願う気持ちが、この一言に凝縮されています。 読んでいる私たちも、この言葉が発せられた瞬間に、これまでのすべてのシーンが鮮やかに蘇るような感覚に陥ります。 ただの奇抜なタイトルだと思っていたものが、読み終える頃には、一生心に残り続ける「愛の言葉」へと姿を変えているのです。

第9章:一歩踏み出す力
「僕」が踏み出した、新しい世界への一歩
彼女がいなくなったあと、彼はふたたび一人で生きていくことになります。 でも、以前の彼とはもう決定的に違っています。 他人を遠ざけ、本の世界だけに閉じこもって自分を守っていた「僕」は、もうそこにはいません。 彼女が身をもって教えてくれた「誰かと関わって生きる」ことの大切さを、彼は自分の足で実践し始めます。 勇気を出して誰かに声をかけることや、自分の素直な気持ちを言葉にして伝えること。 それは、これまでの彼にとっては、エベレストに登るのと同じくらい大きな冒険でした。 でも、彼の中に生き続ける彼女が、その背中を優しく、力強く押してくれているのです。

明日会う人に、優しい言葉をかけたくなる理由
この本を読み終えたあと、いつもの帰り道や、家族が待つ家の扉が、昨日までとは少しだけ違って見えるようになります。 私たちはどうしても、「明日もまた同じように大切な人に会える」と信じて疑いません。 でも、桜良の身に起きたあまりにも突然の出来事を通して、その「当たり前」がどれほど奇跡的なことなのかを痛感させられるからです。 「もっと優しくしておけばよかった」とか、「あんなひどいことを言わなきゃよかった」という後悔は、誰だってしたくないものです。 だからこそ、読み終えたあとの私たちは、今この瞬間に隣にいる人を、もっと大切にしようと思えるようになります。 照れくさくて言えなかった「ありがとう」や、何気ない「お疲れ様」という言葉。 そんな小さな言葉たちが、実は一番大切な「生きている証」なのだと気づかせてくれるのです。
読書が、あなたの「心の栄養」になる瞬間
本を読むという行為は、単に文字を追うことだけではありません。 物語の中の誰かと一緒に笑ったり、泣いたり、深く悩んだりすることで、自分の中に新しい感情の種がまかれていきます。 『君の膵臓を食べたい』を読み切ったあなたは、きっと以前よりも少しだけ、人の心の痛みに敏感になり、優しくなれているはずです。 それは、あなたがこの本を通して、桜良や「僕」と一緒に一生懸命に生きた証拠でもあります。 読書が苦手だった人にとって、この一冊を読み切ったという経験は、大きな自信にもなるでしょう。 心がカサカサに乾いてしまったとき、そっと栄養を与えてくれるような、そんな素敵な力が本にはあるのです。
第10章:なぜ住野よるさんの文章は、こんなに読みやすいのか

難しい漢字や表現を削ぎ落とした「生きた言葉」
さて、最後の章では、この物語がなぜ「読書初心者」にこれほど支持されているのか、その秘密についてお話ししますね。 住野よるさんの文章の最大の特徴は、とにかく「飾っていない」ことです。 難しい熟語や、辞書を引かなければならないような小難しい表現は、ほとんど出てきません。 まるで信頼できる友達から、カフェでじっくりとお悩み相談をされているような、そんな親しみやすい言葉で綴られています。 だからこそ、普段あまり本を読まない人でも、途中で立ち止まることなく、スラスラと物語の世界に入っていけるのです。 「文章を読む」というよりは、「感情を直接受け取っている」ような不思議な感覚。 この心地よさが、多くの人を一気に物語のラストまで運んでいってくれる理由なのです。
アニメや映画とは違う「文字だからこそ伝わる」感情のひだ
この物語は、実写映画やアニメにもなっているので、そちらを先に見たという方も多いかもしれません。 もちろん、映像で見る美しさも素晴らしいのですが、小説には小説にしかできない「魔法」があります。 それは、登場人物たちの「心の声」をダイレクトに聴けることです。 映画では表情だけで読み取らなければいけない微妙な感情も、本の中では丁寧な言葉として綴られています。 誰にも言えない不安や、ふとした瞬間に揺れ動く心のひだが、文字を通じてじわじわと伝わってくるのです。 また、映像は勝手に進んでいきますが、本は自分のペースで読み進めることができます。 「今の言葉、いいな」と思ったら、一度ページをめくる手を止めて、その余韻に浸ることだって自由です。 あなたの頭の中で作り上げられた桜良や「僕」の姿は、世界にたった一つだけの、あなただけの物語になります。 文字でしか味わえない、深く、静かな感動がそこには待っています。
一気に読み進めてしまう、テンポの良い会話劇
「本を読み始めると、途中で眠くなってしまう」という悩みを持っている方も安心してください。 この物語のもう一つの大きな魅力は、まるで目の前で二人がお喋りしているような、テンポの良い会話です。 「僕」と桜良のやり取りは、時にコミカルで、時に鋭く、まるでピンポン玉が行き来するようなスピード感があります。 二人の軽快な掛け合いを追いかけているうちに、気づけば何十ページも読み進めていた、なんてことも珍しくありません。 難しい説明文が延々と続くのではなく、生きた言葉がポンポンと飛び出してくるので、物語の情景が自然と頭に浮かび上がってきます。 この「読みやすさ」こそが、住野よるさんが多くの読者に愛されている最大の理由でもあります。 普段テレビドラマやアニメを楽しんでいる感覚で、気負わずにページをめくってみてください。 きっと、あっという間に物語の終わりまで連れて行ってくれるはずです。
おわりに
最後まで読んでくださって、本当にありがとうございます。 この物語の魅力が、少しでもあなたに伝わっていたら嬉しいです。 最初は「怖いタイトルだな」と思っていた方も、今は少しだけ、その響きが違って聞こえているのではないでしょうか。 本を読むということは、誰かの人生を少しだけお裾分けしてもらうような、とても贅沢な体験です。 もしあなたが今、何かに悩んでいたり、日常に少し退屈を感じていたりするなら、ぜひ本屋さんでこの一冊を探してみてください。 桜良と「僕」が過ごした煌めくような時間は、きっとあなたの心に、小さくて温かい火を灯してくれるはずです。 一冊の本を読み終えたあとの自分は、読み始める前よりも、ほんの少しだけ優しくなれている気がするものです。 そんな不思議な変化を、ぜひあなた自身の手で、ページをめくりながら感じてみてください。 これからも、あなたの日常が素敵な物語との出会いで満たされることを、心から願っています。 次は、本を読み終えたあなたの感想を、ぜひ聞かせてくださいね。 それでは、また次の物語でお会いしましょう。


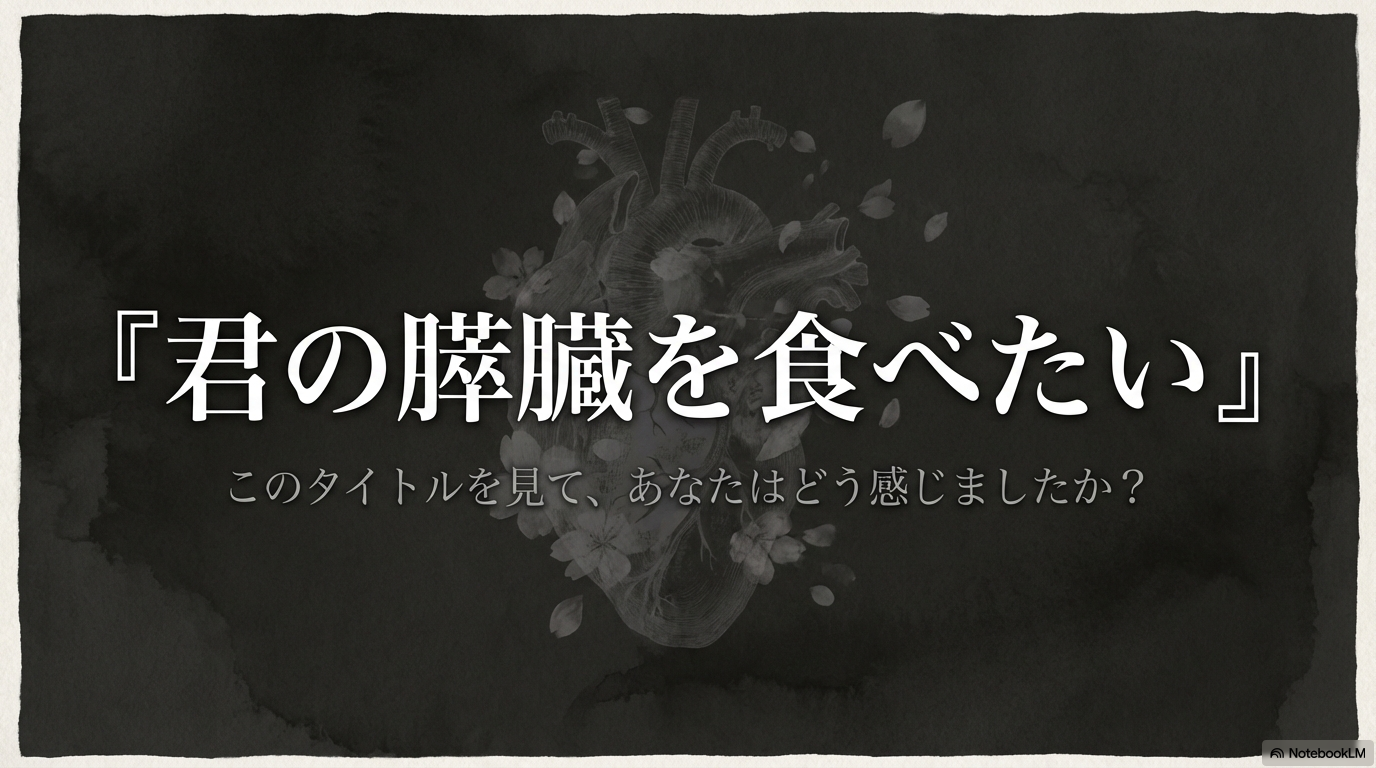









コメント