言いにくいことを伝えるのって、本当に疲れますよね。
業務上の注意や、友人への指摘など、相手を思ってのことなのに、伝え方を間違えて関係がギクシャクした経験はありませんか?多くの場合、問題なのは内容ではなく、その伝え方にあります。伝え方が下手なせいで、不本意に人間関係を悪化させてしまうのはもったいないことです。
「もっとスムーズに、角を立てずに伝えられたら…」
そんな悩みを抱えるあなたにこそ読んでほしいのが、三笠書房から出版されている山﨑武也氏の『気くばりがうまい人のものの言い方』です。本書は、単なるマナーや気遣いの本ではありません。相手の気持ちを尊重しつつ、自分の意図を正確に、そして円滑に伝えるための具体的な「ものの言い方=会話術」が詰まった一冊です。特に、「伝え方」「人間関係」「会話術」といったキーワードで悩みを抱えるビジネスパーソンに強く支持されています。
この記事では、本書の中から、特に「言いにくいこと」をストレスなく伝え、職場の人間関係を劇的に円滑にするための気くばりの極意を厳選してご紹介します。読み終える頃には、あなたのコミュニケーションに対する不安が解消され、自信を持って発言できるようになるはずです。ぜひ最後までご覧ください。
💡「気くばり」とは単なる優しさじゃない!著者が定義する言葉の技術
まず、本書が提唱する「気くばり」の定義を明確にしましょう。山﨑武也氏の言う気くばりは、単に相手に優しく接することや、過度に気を遣うことではありません。むしろ、それは「自分の主張や意思を、相手が気持ちよく受け入れられるように加工する言葉の技術」であり、「結果を出すため」の戦略的なコミュニケーションです。
これは、「伝えるべきことはきちんと伝える」という大前提のもとで成り立っています。 例えば、「資料のミスを指摘する」という場合、気くばりがない伝え方は「このミス、なんで気づかなかったの?」です。これでは相手は責められたと感じ、萎縮してしまいます。
本書が教える気くばりは、「あなたのミスに気づいたよ。でも一緒に解決しよう」という姿勢を言葉に込めることです。この違いが、単なる感情的なやり取りを生産的な対話へと変えていきます。気くばりの本質を理解することで、「言いたいけど言えない」というジレンマから解放されるでしょう。

🗣️実践テクニック①:相手に「YES」と言わせる言い換えの具体例3選
「気くばり」の具体的なテクニックを見ていきましょう。この本では、相手の抵抗感を減らし、前向きな行動を促すための「言い換え」が多数紹介されています。ここでは、すぐに使える3つの例を厳選しました。
1. 否定形を肯定形に変える:「○○ではない」→「○○した方がいい」
❌ 「このプロジェクトは、まだリスクが高い*のではないですか*?」 説得力に欠け、不安を煽るだけで終わってしまいがちです。
⭕ 「このプロジェクトを成功させるには、*この点を強化した方が*より確実です。」 「強化」という前向きな言葉を使い、具体的な解決策を提案する形にすることで、議論が生産的になります。
2. 責任の所在を共有する:「あなたが」→「私たちで」
❌ 「*あなたが*提出した企画書には、数字の根拠が足りません。」 個人攻撃のように聞こえ、相手は防衛的になります。
⭕ 「この企画をより魅力的にするために、*私たちで*数字の根拠をもっと固めましょう。」 「私たちで」という連帯感を示す言葉は、言いにくい指摘を協力の呼びかけに変えます。
3. 感情論を排除する:「いつも」→「具体的に」
❌ 「*いつも*報告が遅いから困ります。」 曖昧な指摘は、相手に改善点が見えず、ただ不満をぶつけられたと感じさせます。
⭕ 「昨日のA案件の報告ですが、*締め切り1時間前*ではなく、*3時間前*にいただけると助かります。」 具体的な事実に基づいて伝えることで、相手は感情的にならずに、何を改善すべきかを理解できます。

🏢実践テクニック②:職場で役立つ!上司・部下への効果的な「ものの言い方」
本書が特に真価を発揮するのは、職場の人間関係です。上司への進言や部下への指導など、デリケートな場面で使えるテクニックを応用して紹介します。
1. 上司への反対意見:「しかし」より「加えて」を使う
上司の提案に異議を唱える際、頭ごなしに「しかし」「でも」と反論すると、敵対的と見なされがちです。
【気くばり術】 「ご提案いただいたA案、大変素晴らしいです。*加えて*、B案のメリットも考慮に入れることで、より盤石な体制が築けるのではないでしょうか。」
一度受け入れた姿勢を見せ(共感)、その上で自分の提案(別案)を付け加えることで、上司の顔を立てつつ、円満に意見をテーブルに乗せることができます。
2. 部下への指導:「命令」より「依頼」で自発性を促す
部下にタスクを依頼する際、一方的な命令形ではモチベーションが上がりません。
【気くばり術】 「この資料作成、君の*得意な分野*だと思うんだ。*力を貸してもらえないかな*。期待しているよ。」
「依頼」の形にすることで、部下は「やらされている」ではなく「期待されている」と感じ、自発的な行動につながります。また、「君の得意な分野」という言葉で承認欲求を満たし、モチベーションを高める効果もあります。

🧘総括:「気くばりの達人」になるためのマインドセットと継続のヒント
本書を通じて一貫して流れているのは、「ものの言い方」を変えることで、自分自身も、相手も、そして周囲の環境もすべて良くするという考え方です。
気くばりの達人になるために、単なるテクニックの学習で終わらせず、以下のマインドセットを常に意識しましょう。
- 相手の立場で考える習慣をつける: 自分が同じことを言われたらどう感じるか?を常にシミュレーションする。
- 感情的にならないための「間」を持つ: 言いにくいことを言う前に、一呼吸置く「間」を意識することで、言葉を選び直す時間を作れます。
- 完璧を目指さない: 多少ぎこちなくても、相手への敬意が伝われば、それが最高の気くばりとなります。
今日から一つずつ、この「気くばりの言い換え」を実践してみましょう。言葉を少し変えるだけで、あなたの人生における人間関係のストレスは劇的に減り、仕事もプライベートも円滑に進むようになるはずです。

🚀まとめ:言葉一つで人生は変わる!今日から実践できる「気くばり」会話術
三笠書房発行、山﨑武也氏の『気くばりがうまい人のものの言い方』は、「言いにくいこと」を円滑に伝えたいすべての人にとって必読の一冊です。
この記事では、本書の核となるメッセージを厳選してご紹介しました。
- 気くばりは単なる優しさではなく、結果を出すための戦略的な言葉の技術である。
- 否定形を肯定形に、個人への責任を連帯に言い換えることで、相手の抵抗感を減らせる。
- 職場では、上司には「加えて」で協調的に、部下には「依頼」で自発性を促すのが効果的。
「あの人、感じがいいね」と言われる人は、才能ではなく、「ものの言い方」の技術を身につけています。本書は、その技術を体系的に学べる教科書のようなものです。
人間関係の悩みは、伝え方を変えるだけでほとんど解消されます。 ぜひこの機会に本書を手に取り、あなたのコミュニケーション能力を劇的に向上させ、ストレスフリーな毎日を手に入れてください!
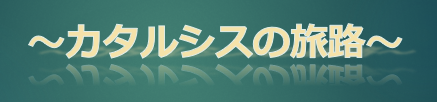

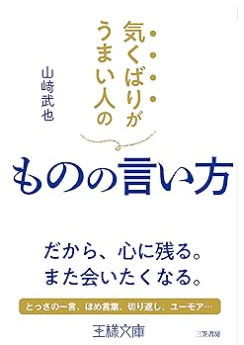

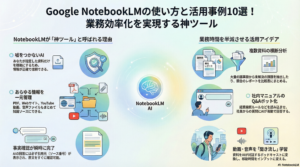
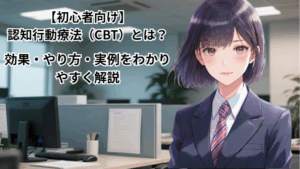
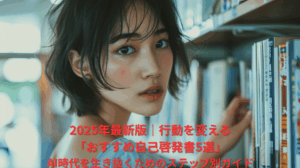

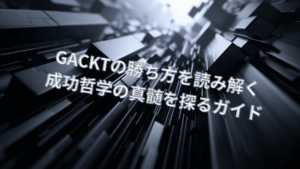


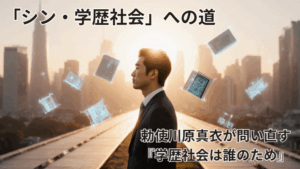
コメント