現代の日本社会において、「学歴社会」という言葉はすでに古びたものだと感じる人もいるかもしれない。
しかし、採用現場や昇進評価の裏側では、依然として「どの大学を出たか」が人材選別の基準として根強く生き続けている。
高学歴であることが安心をもたらし、そうでない人は「努力が足りなかった」と見なされる――。
その構造に、あなたもどこかで理不尽さを感じたことがあるのではないだろうか。
2025年、PHP新書から刊行された勅使川原真衣著『学歴社会は誰のため』は、この長年の構造を社会制度と組織文化の視点から切り裂く一冊である。
本書は、単なる学歴批判でも、努力礼賛の逆張りでもない。
むしろ「なぜ学歴社会が終わらないのか」を冷静に見つめ、その持続を支える“共犯関係”を解明していく。
1. 「学歴社会」を動かす見えない力──企業と教育の共犯関係
勅使川原は、日本における学歴社会の根源を「企業文化と教育機関の共犯関係」に見いだす。
企業は「頑張れる人」「我慢できる人」を採用したい。
だが、面接や短期間の選考では、その“人間的耐性”を見抜くことは難しい。
そこで登場するのが「学歴」だ。
大学受験を乗り越えた人=努力を継続できる人。
この単純な構図が、長年にわたって採用の合理的指標として使われてきた。
教育機関もまた、企業が求める“即戦力ではないが伸びる人材”を輩出することで、自らの価値を保証してきた。
つまり、企業と教育は互いの存在を補完し合い、学歴社会という仕組みを強固に維持してきたのである。

2. メンバーシップ雇用という温床──学歴が評価基準になる理由
日本企業の多くは、職務内容を明確に定義する「ジョブ型雇用」ではなく、
「メンバーシップ型雇用」を採用している。
この仕組みでは、入社時に具体的な職務が決まっていない。
「どんな業務にも対応できる人」を採用したいという前提がある。
だからこそ、採用担当者は“未知の状況にも耐えられる人”を求め、
それを測る代理指標として学歴を使ってきた。
学歴とは、努力・忍耐・社会的適応性の「見えない証明書」でもある。
皮肉なことに、その“見えない証明”こそが、能力評価を曖昧にし、学歴偏重を温存しているのだ。

3. 努力と成果の不一致──学歴社会が生み出す構造的な理不尽
勅使川原は、学歴社会の最大の問題を「努力の方向性と仕事の成果が一致しないこと」に見ている。
受験勉強で磨かれた忍耐力や記憶力は、確かに一定の能力を示す。
だが、実際の職場で求められるのは「状況判断力」や「対人調整力」であり、
これらは学歴とは直接関係がない。
にもかかわらず、学歴が高いというだけで、能力やポテンシャルが高いと見なされる。
このズレが、社会人に深い不信感を生む。
「努力は報われる」という信念が、いつしか「努力の方向を間違えた者が負ける」という皮肉な構造に変わってしまっているのだ。

4. 「親ガチャ」と教育格差──努力の起点が不平等である現実
さらに著者は、学歴社会を支えるもう一つの要素として「家庭背景の格差」を挙げる。
親の学歴や経済状況は、子の教育機会に直接的な影響を与える。
経済的に恵まれた家庭では、塾や習い事、留学などの投資が可能であり、
それが結果的に“学歴レース”での優位を生む。
つまり、学歴社会は努力の公平性を装いながら、
実際にはスタートラインが異なる競争を温存しているのである。
この現実に直面した社会人の多くが、「学歴で人を測ること」に深い違和感を抱くのは当然だろう。

5. 「学歴社会は誰のため」か──問いの本質
タイトルにもなっている問い「学歴社会は誰のため?」は、
単なる哲学的な疑問ではなく、極めて現実的な問題提起だ。
学歴社会は企業のためか。
教育機関のためか。
あるいは、個人の成長や社会の発展のためか。
勅使川原の答えは、ある意味で冷徹である。
学歴社会は「誰のため」でもなく、「仕組みを維持するため」に存在している。
つまり、制度が制度を支える自己循環構造なのだ。
この冷徹な分析は、多くの社会人にとって衝撃的だ。
しかし同時に、それを理解することが、「どう生きるか」を再定義する出発点にもなる。

6. 「シン・学歴社会」──新しい評価軸への提案
本書の核心は、学歴社会の“否定”ではなく、その“再構築”にある。
勅使川原は「シン・学歴社会」への移行を提唱する。
それは、学歴を完全に排除する社会ではない。
むしろ、学歴を一つの情報として活かしつつ、
個人の能力・成果・価値観をより多面的に評価する社会への進化を意味する。
例えば、以下のような変化が求められている。
- 職務要件の明確化:何を求め、何を評価するのかを企業が明示する。
- 学びの可視化:資格・リスキリング・自己学習を学歴と同等に評価する。
- 社会的報酬の再定義:年功や所属ではなく、貢献や創造性に報いる。
この「シン・学歴社会」こそ、努力と成果が再び接続される社会である。

7. 「勅使川原真衣」という思想家──実務と思想をつなぐ知性
勅使川原真衣は教育学と組織論を架橋する研究者であり、
現場の実態を踏まえた社会構造分析に定評がある。
『学歴社会は誰のため』では、抽象的な理論ではなく、
企業人事や教育現場のリアルな声を取り上げながら、
日本社会が抱える「構造的な惰性」を浮き彫りにしている。
彼女の主張は決して感情的ではなく、
むしろ冷静な観察と分析によって読者に“思考の余白”を与える。
この姿勢こそ、まさに本質的な知性の証である。

8. 社会人として「学歴」をどう捉え直すか
読者であるあなたがもし、学歴社会に不満や不信感を抱いているなら、
それは決して間違っていない。
むしろ、その違和感こそが、新しい生き方を模索する知的なサインだ。
重要なのは、「学歴に代わる価値」を自らの中で定義し直すことだ。
資格でも肩書でもなく、思考力・共感力・再現力など、
職場で発揮できる具体的な能力を磨くことが、新時代の武器になる。
そして、自分の学びの軌跡を「可視化」していく。
読書・研修・プロジェクト経験など、あらゆる学びを言語化し、
「私の学びは、学歴以上に価値がある」と自信を持って示すことが、
“シン・学歴社会”を生き抜く第一歩となるだろう。

9. 「学び直し」の時代に生きるということ
勅使川原の提言は、単なる制度改革ではなく、
私たち一人ひとりの“学びの在り方”にも直結している。
大学受験で終わる学びではなく、
社会に出てからこそ深まる学び。
キャリアの中で常に更新される知識と経験。
その連続こそが、「学歴」という過去の称号を超える力になる。
リスキリング、自己啓発、越境学習――これらのキーワードは、
もはや一部の意識高い人だけのものではない。
「学び続けること」が、個人の尊厳と生存戦略を支える時代なのだ。

10. 結論──「学歴社会は誰のため」ではなく「学び社会は誰とつくるか」へ
『学歴社会は誰のため』は、学歴主義という硬直した構造に対して、
「否定」ではなく「再構築」という希望を提示する書である。
学歴社会を嘆くのではなく、
その外側に新しい価値を築く――。
それが、勅使川原真衣の言う「シン・学歴社会」への第一歩だ。
そして今、問うべきはこうだ。
「学歴社会は誰のため」ではなく、
「学び社会は誰とつくるか」。
私たち一人ひとりの意識と行動が、
この社会の評価軸を少しずつ変えていく。
それが、この本が社会人に投げかける最も本質的なメッセージである。

参考文献:
勅使川原真衣『学歴社会は誰のため』(PHP新書、2025年)
出典;Amazon 学歴社会は誰のため (PHP新書) 新書 勅使川原 真衣 (著)
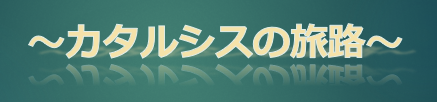

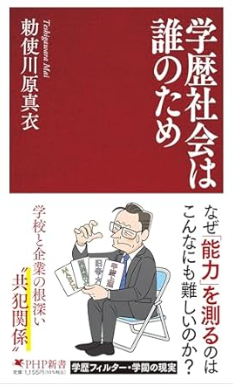

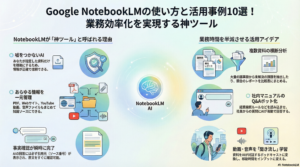
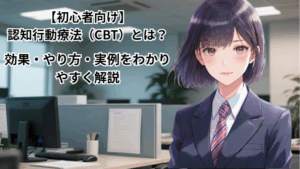
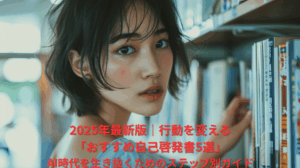

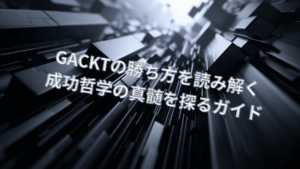



コメント
コメント一覧 (2件)
This is a great breakdown! For those diving deeper into AI tools, check out the AI Girlfriend section on tyy.AI – it’s a fantastic resource for niche AI solutions.
Who doesn’t love a bonus?! Keep an eye on the BHT Club bonus page for the latest deals and promotions. Might get lucky… bhtclubbonus